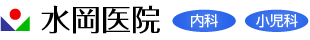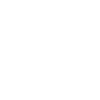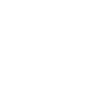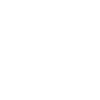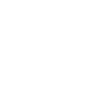ここからは個人的見解を含みます。
新型コロナウイルス
新型コロナウイルスの感染感染拡大が止まりません。
新型コロナウイルスの感染力はインフルエンザウイルスとあまり変わらないようです。感染経路は飛沫感染と接触感染で同じです。なのに世界的に感染が拡大しているのは何故でしょうか?
ウイルス側の要因としては、新型コロナウイルスは接着性がより高く手につきやいため、感染拡大は人の行動によるところが大きいと考えます。要するに、接触感染のリスクは高いだろうということです。ひょっとすると、感染しなくても人の手が媒介してウイルスを広めているという可能性も考えられます。案外お金やスマホにはウイルスが付着しているかもしれません。
また、インフルエンザウイルスの潜伏期はほぼ1日ですが、新型コロナウイルスは5、6日といわれています。インフルエンザは突然発症するのでわかりやすく、早期に対応できますが、新型コロナウイルス感染症は軽症のことが多く、発症してからも通常の生活をしていて、知らない間に感染を広めている可能性があります。
スーパースプレッダー
10人以上への感染拡大の感染源となった患者を「スーパー・スプレッダー」と呼びます。大阪のライブハウスからの急激な感染拡大は記憶に新しいところです。SARS、MARSは流行した際にもスーパー・スプレッダーの存在が指摘されていましたが、どのような人がスーパー・スプレッダーになるのかは不明です。
新型コロナウイルス感染症は重症度に関わらず、感染者の8割は他人に感染させておらず、残りの2割の人から2次感染が起きています。この2割の人はスーパー・スプレッダーになり得るわけですが、適切な予防をすればスーパースプレッダーからの感染拡大はコントロールできるはずです。
幸い日本人は衛生に対する意識が高く、マスク着用率も非常に高い。感染予防にはマスクは意味がないという意見はありますが、私は、マスクは無症状のスプレッダーが使用することで感染拡大を抑えている可能性があると考えています。
さらに私の見解ですが、日本の感染者数を抑えてきた一番の要因は、スプレッダーの多くが、マスクのみならず、感染を拡大させないような行動ををとっていることだと考えています。しかし、一部の人は違う行動をしています。先ほども述べましたが、スーパースプレッダー1人は10人以上に感染させますので、「ちょっとくらい大丈夫」は、いずれ大きな感染拡大につながり、自らに跳ね返ってきます。誰がスプレッダーなのかは発症後でしかわからないので、全ての人が同じ意識を持って行動しないと感染はなかなか減少しません。
日本の新型コロナウイルス感染症発生者数が、世界各国と比較して明らかに少ないということで、世界から注目されています。「PCR検査を行った症例が少ないからで、実際はもっと多くいるはずだ」という意見があります。確かにそうかもしれませんが、患者数の増加スピードをみる限り、無症状のコロナ陽性者だけが多くの割合でいるとは思いません。しかしながら、このまま患者数が増加すれば医療崩壊は起こります。
マスク不足が問題になっています。我々にとってはマスクは仕事上の必需品ですが、マスクは主に飛沫感染を防ぐのが目的で、マスクだけで感染がコントロールできるものではありません。目に見えない接触感染をコントロールするための「行動」こそが重要だと考えます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止
行動の要点は、かからない、うつさない、うつりやすい環境を避けるです。
そのために、
3つの「蜜」を避ける
①換気の悪い密閉空間
➁多くが集まる密集場所
③間近で会話や発声をする密接場所
3つがそろう場所は集団発生の危険がある場所ですので、こういう環境は避けましょう。
咳エチケット
咳やくしゃみで飛沫とともにウイルスが飛び散るのを防ぎます。
咳やくしゃみをする時に、
✕何もしない
条件にもよりますが、2メートル以内の人が飛沫感染する可能性があるので✕
✕手で押さえる
その手で触ったところにウイルスが付着する可能性があるので✕
○マスクを着用する
布マスクは目が粗いので、完全には飛沫を防止できないと考えたほうがいいでしょう。
〇ハンカチやティッシュで押さえる
使用したティッシュは速やかにゴミ箱へ。ハンカチは早めに洗濯を。
○とっさの時は袖で押さえる
マスクなどがないときは袖で押さえるように。服は洗濯したほうがいいでしょう。
いずれの場合もそのあとは手洗いをしましょう。
手洗いは正しく行えていますか?
<手洗い方法(石鹸液)>
1.手指を流水で流す
2.石鹸液を手に取って、手のひらをこすり合わせてよく泡立てる。
3.手の甲 → 指の間 → 親指 → 手のひら、指先 → 手首ともみ洗いを行う。
4.流水でよくすすぐ。
5.ペーパータオルでよく水気を拭き取る。
私はこれを2回転行っています。洗浄後はアルコール消毒を行えばより効果的ですが、消毒液も入手困難なんですよね。
面倒ですが、きっちり行えば接触感染は予防できます。ネットでは写真やイラスト、動画などで分かりやすく説明したものがみられるので検索してみてください。3つの「蜜」を避ける行動とともに、ウイルスがどこにいるかを考え、ウイルスを体内に入れないよう、また媒介しないようにしましょう。